こんにちは!Geminiの力を借りて、独学での中小企業診断士合格に挑戦中のマンダリンです。
この8月と9月は、経済学・経済政策の過去問でコンスタントに60点以上を取れるようになることを目標に、学習を進めてきました。
現在の状況ですが、過去問をランダムに解いてみると、60点を超えられる日もあれば、残念ながら下回ってしまう日もある、といった具合です。まだまだ安定には程遠いですが、全体的には概ね計画通りに進んでいるかな、と感じています。
そして何より、この2ヶ月の試行錯誤の中で、今後の学習をさらに加速させてくれそうな、大きな発見もありました。この記事では、私のリアルな学習記録と、試行錯誤の中で見えてきたブレークスルーの瞬間を共有します。中小企業診断士の勉強法やモチベーション維持に悩んでいる方の、何か少しでもヒントになれば嬉しいです。
当初の計画:2ヶ月で経済学をコンスタントに60点以上
8月、私は意気込んでいました。「この2ヶ月で経済学・経済政策を徹底的にやり込むぞ!」と。計画通り、9月の終わりには過去問でコンスタントに60点以上を取れるようになることを目標に設定しました。
現在のところ、その目標は概ね達成できていると思っています。過去問を解くと、60点以上のラインをコンスタントに超えられるようになってきました。
ただ、油断はできません。超えてはいるものの、ほとんどがギリギリ60点のライン。少し問題の出方や分野が変わるだけで、すぐに50点台に落ちてしまいそうな不安も感じています。しかし、この不安こそが、私を次のブレークスルーへと導いてくれました。
現実:ギリギリ60点の壁と、見えた確かな手応え
コンスタントに60点を取れるようになったとはいえ、まだ「得点源」と言えるレベルではありません。この「ギリギリ60点」という壁を破るには、ただ問題を解き、解説を読むだけでは限界があると感じていました。
何が自分の理解を妨げているのか。どこが知識の抜け穴なのか。この曖昧なモヤモヤが、何度解いてもケアレスミスや「なんとなく」で正解してしまう問題をなくせない原因だと気づきました。
私を救ったブレークスルー。Gemini「間違い解説プロンプト」の進化
停滞を打ち破ってくれたのは、やはり Geminiに「自分が間違えた過去問を解説させる」 という学習習慣でした。特に、プロンプトに含める情報を工夫したことが、私の学習の質を劇的に変えてくれたのです。
【実録】私が実際に使った「間違い解説プロンプト」
以前はただ「間違えたから解説して」と聞くだけでしたが、それだけでは表面的な理解に留まりがちでした。そこで、「自分の思考プロセス」も一緒に伝えるようにしたところ、Geminiがまるで私の思考のクセを診断してくれるかのように、的確な解説を返してくれるようになりました。
以下が、私が実際に使っているプロンプトのテンプレートです。
以下の過去問について、私の理解状況を踏まえた上で、詳細な解説をお願いします。
# 過去問の情報
## 問題文
[ここに問題文を貼り付けてください]
## 選択肢
ア:[選択肢アの内容]
イ:[選択肢イの内容]
ウ:[選択肢ウの内容]
エ:[選択肢エの内容]
## 正解
[正解の記号(例:ウ)]
# 私の理解状況と疑問点
## 1. 私が選んだ選択肢(または考え)
* 私が選んだ解答:[ア/イ/ウ/エ のいずれか、または「分からなかった」と入力]
* その選択肢を選んだ理由:[なぜその答えだと思ったのか、簡単な根拠を入力]
## 2. 理解できている(と思う)点
* [ここに、ご自身が理解していると感じる点を箇条書きで入力]
## 3. 特に知りたい点(不明点)
* [ここに、分からなかったことや疑問点を具体的に箇条書きで入力]
# 解説の指示
上記の「過去問の情報」と「私の理解状況」をすべて考慮し、以下の形式で解説してください。
特に、私が「3. 特に知りたい点(不明点)」で挙げたポイントについては、重点的に、そして私が根本から納得できるように、可能な限り分かりやすく丁寧な解説をお願いします。
## 1. 問題のテーマと論点
* この問題は、どの科目のどのテーマについて問うていますか?
* 解答するために最も重要な「論点(キーとなる知識)」は何ですか?
## 2. 解答への思考プロセス(あなたの思考を添削する形で)
* **(私の思考との比較)**:私が選んだ選択肢やその理由について、どの点が正しく、どの点に誤解があったのかを指摘してください。
* **(問題文の着眼点)**:この問題を解く上で、まず問題文のどこに注目すべきかを解説してください。
* **(各選択肢の検討)**:各選択肢をどのように検討すればよいですか?
* **正解の選択肢の解説**:なぜその選択肢が「正しい」のか、その根拠を詳しく説明してください。
* **不正解の選択肢の解説**:他の選択肢が「なぜ誤り」なのか、一つずつ具体的に説明してください。
## 3. 知識の定着と応用
* この問題の論点について、覚えるべき重要キーワードや概念を3つ挙げてください。
* この知識は、他にはどのような形で出題される可能性がありますか?
Geminiとの二人三脚で見えた課題と解決策
このプロンプトを渡す中で、一つ課題も見えてきました。経済学・経済政策の過去問には、グラフを読み解く問題が多いため、テキストだけで伝えると、Geminiがグラフの状況を誤解し、結果として誤った解説が出力されることがあったのです。
そこで、少し時間はかかりますが、過去問のグラフを画像として取り込み、特に注意してほしい部分に印や矢印を書き込んだ上で、その画像と一緒にプロンプトに含めて聞くようにしました。このひと手間を加えることで、解説の精度が格段に上がり、本当の意味で問題の意図を理解できるようになりました。
次の課題と、「忘却」と戦うための戦略
さて、10月からは気持ちを切り替え、新たな科目「財務・会計」の学習に進みます。経済学はコンスタントに60点を取れるようになったものの、正直、大きな不安があります。
それは、「せっかく身につけた経済学の知識を、次の2ヶ月で忘れてしまったらどうしよう」という、知識の定着と忘却との戦いです。
しかし最近、この「忘却」に対する考え方が少し変わってきました。忘れること自体は、人間の脳の仕組みとして避けられない。大切なのは、忘れたことを思い出すプロセスこそが、記憶をより強固に定着させてくれるのではないか、ということです。忘れることを恐れるのではなく、むしろ記憶を強化するチャンスと捉えようと思い始めました。
そこで、この考えに基づいた具体的なアクションプランを立てました。それは、「2週間に1度、AI(Gemini)を使って経済学・経済政策のオリジナル模試を作成してもらい、それを解く」というものです。
この方法なら、定期的に全範囲に触れることで知識の抜け漏れをチェックできますし、忘れていた部分を効率的にあぶり出して「思い出す」きっかけを強制的に作ることができます。新しい科目に集中しつつも、既存の知識を錆びつかせないための戦略として、これから試していこうと考えています。
4. 記事の締めと読者へのメッセージ
中小企業診断士の勉強は、本当に計画通りには進まないことばかりですよね。思うように結果が出ず、モチベーションが下がる日もあると思います。
でも、こうやって一つずつ壁を乗り越え、自分なりの勉強法を見つけていく過程そのものが、合格への道なんだと信じています。
皆さんは、複数科目の知識をどうやって維持していますか?もし効果的な復習方法や工夫があれば、ぜひコメントで教えてください!一緒に頑張りましょう。
ちいさなことからコツコツと、それでは。
【AI活用に関するご案内】
この記事の作成にあたっては、内容の正確性と分かりやすさを追求するため、一部AIによるサポートを受けています。最終的な内容は、運営者マンダリンの責任において編集・公開しております。
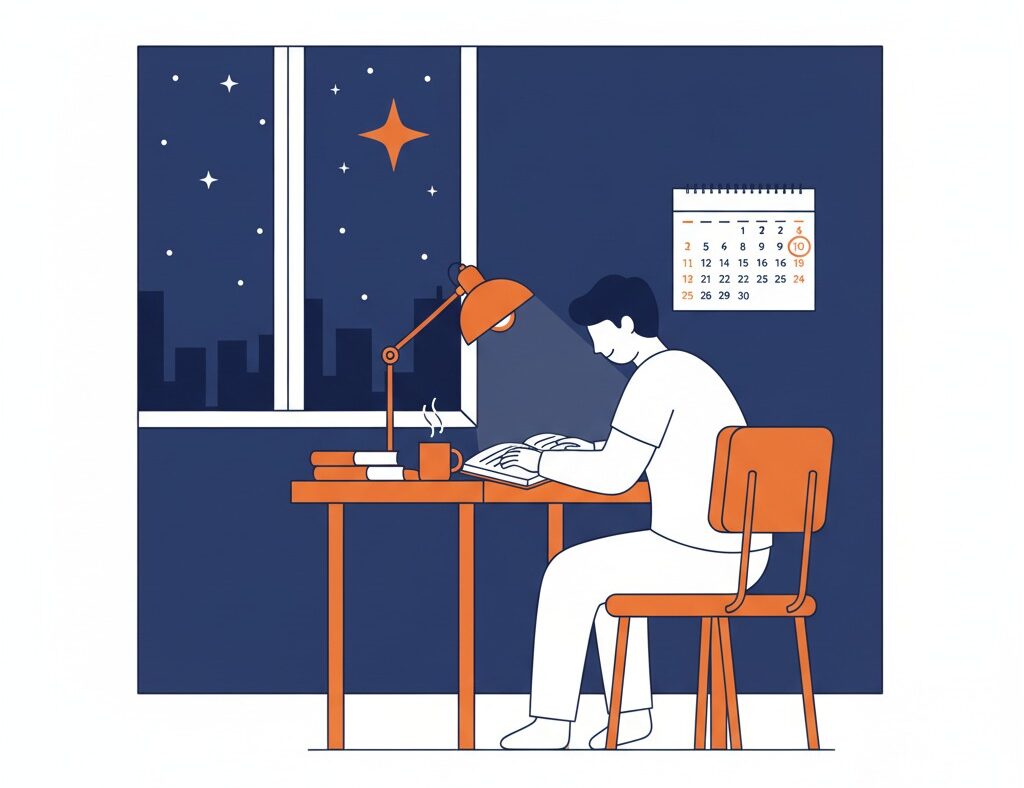


コメント