こんにちは!Geminiの力を借りて、独学での中小企業診断士合格に挑戦中のマンダリンです。
10月から本格的に取り組んでいる「財務・会計」ですが、正直に言うと、60点の壁に苦戦しています。過去問を解いても、安定して合格点を超えることができず、もどかしい日々が続いていました。
ですが、この1ヶ月半で私の勉強法は大きく進化しました。『Gemini』による深い理解、そして新たな相棒『NotebookLM』による実践演習。この二刀流に、確かな手応えを感じています。
この記事では、私の財務・会計とのリアルな格闘の記録と、学習を加速させたAI二刀流の具体的な使い方を共有します。同じように苦しんでいる方の、何か一つでもヒントになれば嬉しいです。
【目標60点の壁。財務会計のリアルな現在地】
10月から11月中旬にかけての目標は、「財務・会計の過去問でコンスタントに60点以上を取れるようになる」ことでした。しかし、あと半月を残す現時点での自己評価は、「問題の傾向によってはギリギリ60点を超えるレベル」。正直、計画通りに進んでいるとは言えません。
特に課題となっているのが、細かい知識の定着と、計算問題への対応力です。
- 細かい用語の理解: 選択問題で、似たような用語や概念の違いを正確に理解できておらず、最後の二択で間違えてしまう。
- 計算要素の抜き出し: 問題文の中から、どの数値をどの計算式に当てはめればよいのか、瞬時に判断することに迷いが生じてしまう。
解説を読めば「なるほど」と理解はできるものの、いざ初見の問題に向き合うと手が止まってしまう。この「分かっているつもり」の状態を打破する必要がありました。
【学習法が進化!GeminiとNotebookLMの「AI二刀流」】
このもどかしい状況を打破するキッカケとなったのが、AIツールの役割分担、いわば「AI二刀流」の確立です。これが、この1ヶ月半における最大の収穫でした。
「なぜ」を深く理解するGemini
まず、これまで通りGeminiには「家庭教師」として、深い理解をサポートしてもらっています。間違えた過去問について、単純に解説を要約させるのではありません。
「なぜ、この勘定科目は販管費ではなく営業外費用になるの?」
「このCF計算書の公式が、なぜこのような構造になっているのか、小学生にも分かるように教えて」
このように、自分が納得できるまで「なぜ?」を繰り返し質問することで、知識が点から線へと繋がっていく感覚を得られました。曖昧だった用語の理解も、Geminiとの対話を通じて、その本質的な意味を掴めるようになってきました。
「演習量」を無限にこなすNotebookLM
そして、今回新たに導入したのが『NotebookLM』です。これが、私の計算問題への向き合い方を劇的に変えました。
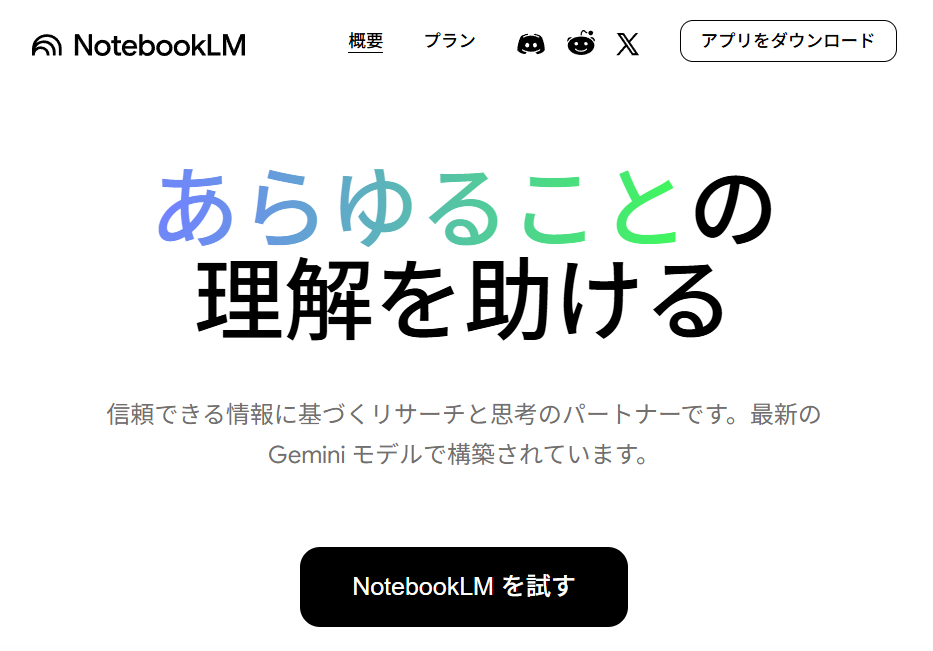
NotebookLMのすごいところは、自分がアップロードしたPDFやテキスト(ソース)に基づいて、質問に答えたり、新しい文章を生成したりできる点です。私は、令和6年までの過去問と解答のPDFをソースとしてアップロードしました。
そして、このように依頼するのです。
「ソースに含まれる、経営分析のCVP分析の問題を参考に、売上高や固定費、変動費率の数値だけを変えたオリジナル問題を5問作成してください。」
ソースにした過去問をもとにオリジナル問題が生成されることで、特定分野の演習量を圧倒的に確保できるようになりました。
もちろん、生成AIが作る問題なので、時には問題文がおかしかったり、解答自体が間違っていることもあります。
そのため、全てを鵜呑みにするのではなく、「この問題文は適切か?」「AIの解答は本当に正しいか?」と、自分の解答と照らし合わせながら、一つひとつ吟味する作業が欠かせません。
この一手間が、結果的により深い理解に繋がっていると感じています。
「理解はGemini、演習はNotebookLM」。この役割分担を確立したことで、知識のインプットとアウトプットが非常にスムーズに回転し始め、計算問題への苦手意識が確かな手応えに変わりつつあります。これは、独学者にとってまさに革命的なNotebookLM 活用法と言えるかもしれません。
【見えてきた次なる壁。「計算スピード」をどう克服するか】
AI二刀流によって、解き方の「理解度」は格段に上がりました。しかし、それと同時に新たな壁、そして中小企業診断士試験の本質的な難しさが浮き彫りになりました。
それが、「計算スピード」です。
一問一問、時間をかければ正解にたどり着けるようにはなりました。しかし、本番の試験時間内に全問を解ききることを考えると、今のスピードでは到底間に合いません。まさに、時間切れによる失点を危惧している状況です。
しかし、これは悲観すべきことではなく、自分が次のステージに進んだ証拠だとポジティブに捉えています。これからの半月、そして本番までの課題は明確です。「時間内に解ききる力」を徹底的に鍛え上げます。
具体的には、NotebookLMで生成した問題を「1問5分」などと時間を計って解くトレーニングを習慣化し、スピードと正確性の両立を目指します。
記事の締めと読者へのメッセージ
一つの壁を越えると、また新しい壁が見えてくるのが、この試験の難しいところであり、面白いところでもありますよね。
AIという強力な相棒を得て、ようやくスタートラインに立てたような気がしています。これからも試行錯誤しながら、一歩ずつ前に進んでいきたいと思います。
最後に、皆さんに質問です。
皆さんは、計算スピードを上げるためにどんな工夫をしていますか? おすすめの訓練法や、時間配分のコツなどがあれば、ぜひコメントで教えてください!
【AI活用に関するご案内】
この記事の作成にあたっては、内容の正確性と分かりやすさを追求するため、一部AIによるサポートを受けています。最終的な内容は、運営者マンダリンの責任において編集・公開しております。
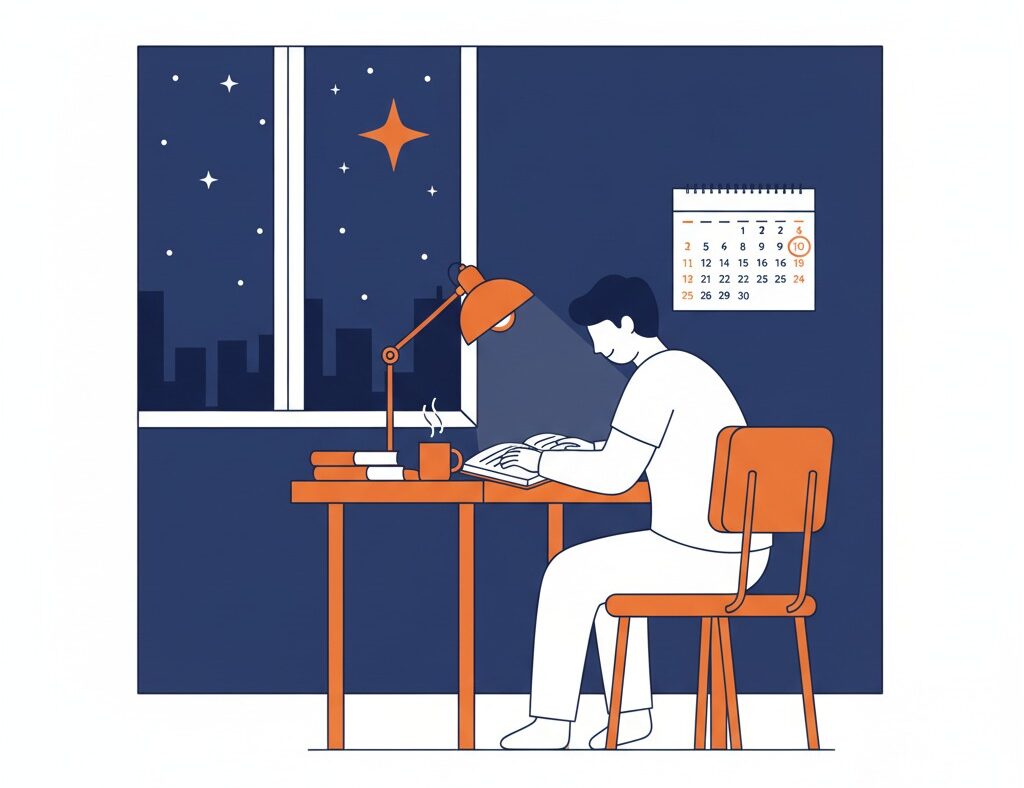


コメント