こんにちは!Geminiの力を借りて、独学での中小企業診断士合格に挑戦中のマンダリンです。
経済学の「AD-AS分析」と「IS-LM分析」、それぞれのグラフは理解できても、2つの関係性、特に「傾きがどう影響し合うのか」という論点で悩みますよね。
私も「貨幣需要の利子弾力性」なんて言葉が出てきた瞬間に思考停止してしまいました。
結論から言うと、この複雑な関係性は、Geminiが作ってくれた『AD王国と、経済をうるおす魔法の水路』という物語を読めば一発で記憶できます。
この記事では、その物語が生まれるきっかけとなった私の失敗談も交えながら、Geminiと一緒に知識を定着させるプロセスを全公開します。
【中小企業診断士】令和5年度再試験で撃沈!AD-AS分析とIS-LM分析の深い関係
経済学の勉強を進めていると、必ず出会うのがAD-AS分析とIS-LM分析です。
私はこれらを全く別の単元だと勘違いしていたため、令和5年度の再試験問題で、見事に撃沈しました…。
まずは、その恥ずかしい失敗談からご覧ください。
問題文と私の恥ずかしい解答
【出典】: 令和5年度 再試験 経済学・経済政策 第10問 設問1
正解:エ
【私の最初の解答】
私は選択肢「オ」を選びました。
「投資の利子弾力性が大きいってことは、利子率がちょっと変わるだけで投資がすごく増減するから、AD曲線は緩やか(水平に近く)なるはず…だからcは誤。でも、貨幣需要の利子弾力性や所得弾力性については、どんな状況なのか全くイメージできなくて、とりあえず全部誤だろう!」
という、なんとも情けない理由でした。
つまずきの核心は「無関係」という思い込み
私のつまずきの根本原因は、「AD-AS分析とIS-LM分析は、まったく別のものだと思っていた」ことです。
それぞれが独立したグラフ分析だと考えていたため、IS曲線やLM曲線の傾きが、AD曲線の傾きに影響を与えるという発想自体がありませんでした。
この致命的な勘違いを、私の学習パートナーであるGemini(ChatGPTと同じ生成AIの一種です)に相談したところ、目からウロコの解説が返ってきました。
Geminiが解説!AD曲線はIS-LM分析の「影」から生まれる
Geminiの解説によると、AD曲線はIS-LM分析から導き出される、いわば「影」のような存在だというのです。
ここで、読者の皆さんが抱えるであろう疑問点も踏まえながら、その関係性を解説します。
なぜAD曲線は右下がり?IS-LM分析からの導出プロセス
AD(総需要)曲線とは、縦軸に「物価」、横軸に「実質GDP」をとったグラフです。
そして、この曲線はIS-LM分析の結論を別の角度から見たものなのです。
- 物価が下落する
- 実質貨幣供給量(M/P)が増える
- LM曲線が右にシフトする
- 利子率が下がる
- 企業の投資が増える
- 実質GDPが増加する
つまり、「物価が下がると、実質GDPが増える」という関係が成り立ちます。この「物価」と「実質GDP」の関係だけを抜き出して描いたのがAD曲線。
だから、AD曲線は右下がりのグラフになるのです。
読者の疑問を解消!3つの「弾力性」と傾きの複雑な関係
ここからが本題です。問題文に出てきた3つの「弾力性」が、IS曲線とLM曲線の傾きを変化させ、その結果、AD曲線の傾きにどう影響するのかを整理します。
- a. 貨幣需要の利子弾力性が大きいと…
- LM曲線は緩やかになります。
- 緩やかなLM曲線が右にシフトしても、利子率の低下幅は小さくなります。
- 利子率があまり下がらないので、投資の増加も小さくなります。
- 結果、GDPの増加幅も小さくなります。
- 物価が下がってもGDPがあまり増えないので、AD曲線は急になります。→ よって、aは「正しい」
- b. 貨幣需要の所得弾力性が小さいと…
- LM曲線は緩やかになります。
- ロジックはaと全く同じです。LM曲線が緩やかになるため、物価が下がってもGDPの増加幅は小さくなります。
- したがって、AD曲線は急になります。→ よって、「緩やかになる」としたbは「誤り」
- c. 投資の利子弾力性が大きいと…
- IS曲線は緩やかになります。
- 物価下落でLM曲線が右にシフトし、利子率が少し下がっただけでも、投資が大きく増加します。
- 結果、GDPの増加幅は大きくなります。
- 物価が下がったときにGDPが大きく増えるので、AD曲線は緩やかになります。→ よって、「急になる」としたcは「誤り」
この複雑な因果関係、文章だけだと混乱しますよね。
そこで、Geminiがこの関係性を一瞬で覚えられる物語を作ってくれました。
【補足】AS曲線が垂直になるのはなぜ?
ちなみに、問題の図でAS(総供給)曲線の一部が垂直になっていますが、これは「完全雇用」の状態を表しています。
世の中にある労働力や設備をすべて使い切っているため、物価がどれだけ上がっても、それ以上生産量(実質GDP)を増やすことができない状態です。
これは特に「古典派」の経済学の考え方に基づいています。
Geminiが創作!この論点が10秒で記憶できる『AD王国と、経済をうるおす魔法の水路』
Geminiに「物語を作って」とお願いすると、一回で完璧な答えが出てくると思いがちですよね。
でも、実はこの『魔法の水路』の物語も、一発で完成したわけではありません。
最初にGeminiから出てきたアイデアは、どうも私の頭の中でスッと映像にならなかったんです…。
これでは、読者の皆さんにも伝わらない!と思い、条件を少しずつ変えながら、何度か作り直しをお願いしました。
いわば、Geminiとの共同作業による試行錯誤ですね。
そして、ようやくたどり着いたのが、この物語です
【物語】AD王国と、経済をうるおす魔法の水路
むかしむかし、国民所得(GDP)の豊かさで国力が決まる「AD王国」がありました。この国の豊かさは、天にある水源から「LM水路」と「IS水路」という2つの魔法の水路を通って、大地(国民所得)にどれだけ水が注がれるかで決まります。
すべての始まりは「物価下落」という恵みの雨。雨が降ると水源の水かさが増し、水路に水が流れ込みます。
最初の関門は「LM水路(LM曲線)」です。この水路は、流れる水の勢いを「水圧(利子率の低下幅)」に変える役割があります。
この水路の傾斜がなだらか(=LM曲線が緩やか)だと、水の勢いは弱まり、水圧はあまり高まりません。このなだらかな傾斜は、「貨幣需要の利子弾力性が大きい」または「貨幣需要の所得弾力性が小さい」ときに起こります。
次に水が通るのが「IS水路(IS曲線)」です。この水路には最後の蛇口がついており、LM水路から来た水圧を受けて、最終的に大地に注がれる水の量(投資)を決めます。
この蛇口がユルユル(=IS曲線が緩やか)だと、弱い水圧でも大量の水が流れ出します。このユルユルの蛇口は「投資の利子弾力性が大きい」ときに現れます。
さて、AD王国の土地の形(AD曲線の傾き)はどう決まるでしょう?
大地に流れ込む水の量(GDPの増加幅)が多ければ、広くうるおい、土地の起伏は緩やかになります。逆に、水の量が少なければ、土地はうるおわず起伏は急なままです。
つまり、
- LM水路がなだらか(緩やか)だと、そもそも水圧が弱まるので、最終的に大地に届く水の量は少なくなります。だから、AD王国の土地は急になります。
- IS水路の蛇口がユルユル(緩やか)だと、どんなに水圧が弱くても、それを補ってあまりある大量の水が流れ出します。だから、AD王国の土地は緩やかになります。
【物語の解説】
この物語で、複雑な関係性をスッキリ整理しましょう。
- IS曲線が緩やか(蛇口がユルい) → 最終的な水の量(GDP)が増えやすい → AD曲線は緩やか。
- LM曲線が緩やか(水路がなだらか) → 水圧が弱まり、最終的な水の量(GDP)が増えにくい → AD曲線は急。
「LMが緩やかだと、ADは急」「ISが緩やかだと、ADも緩やか」。
この逆の関係と理由が、水路と蛇口のイメージで直感的につながりませんか?
まとめ:今日の学びを自分の血肉に変える
今回は、経済学の「AD-AS分析とIS-LM分析」の関係性について、私の失敗談とGeminiの力を借りた学習プロセスをご紹介しました。
- AD曲線はIS-LM分析から導出される。
- IS曲線・LM曲線の傾きがAD曲線の傾きを決めるが、その影響は逆!
- IS曲線が緩やかになる(投資の利子弾力性が大きい)→ AD曲線は緩やかになる。(ユルい蛇口)
- LM曲線が緩やかになる(貨幣需要の利子弾力性が大きい、または所得弾力性が小さい)→ AD曲線は急になる。(なだらかな水路)
この関係性を『AD王国と、経済をうるおす魔法の水路』のイメージと一緒にインプットすれば、もう傾きの問題で迷うことはありません!
記事の締めと読者へのメッセージ
いやー、経済学って本当に奥が深いですよね!
一度間違えても、こうして理由をしっかり理解し直せば、知識はさらに強固になります。
皆さんも、間違いを恐れずに学習を進めていきましょう!
皆さんが使っているユニークな覚え方もぜひコメントで教えてください!
Geminiと考えたこの『魔法の水路』の物語、どう思いますか?
感想も聞かせてもらえると嬉しいです!
独学は孤独だけど、こうやってGeminiを相棒にするのも面白いですよね。
ちいさなことからコツコツと、それでは。
【AI活用に関するご案内】
この記事の作成にあたっては、内容の正確性と分かりやすさを追求するため、一部AIによるサポートを受けています。最終的な内容は、運営者マンダリンの責任において編集・公開しております。

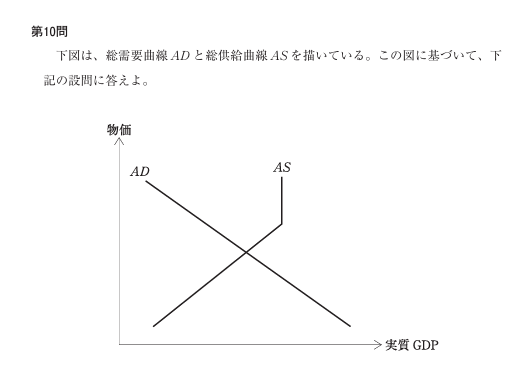
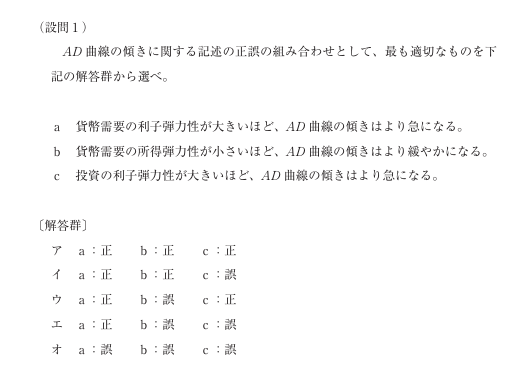

コメント